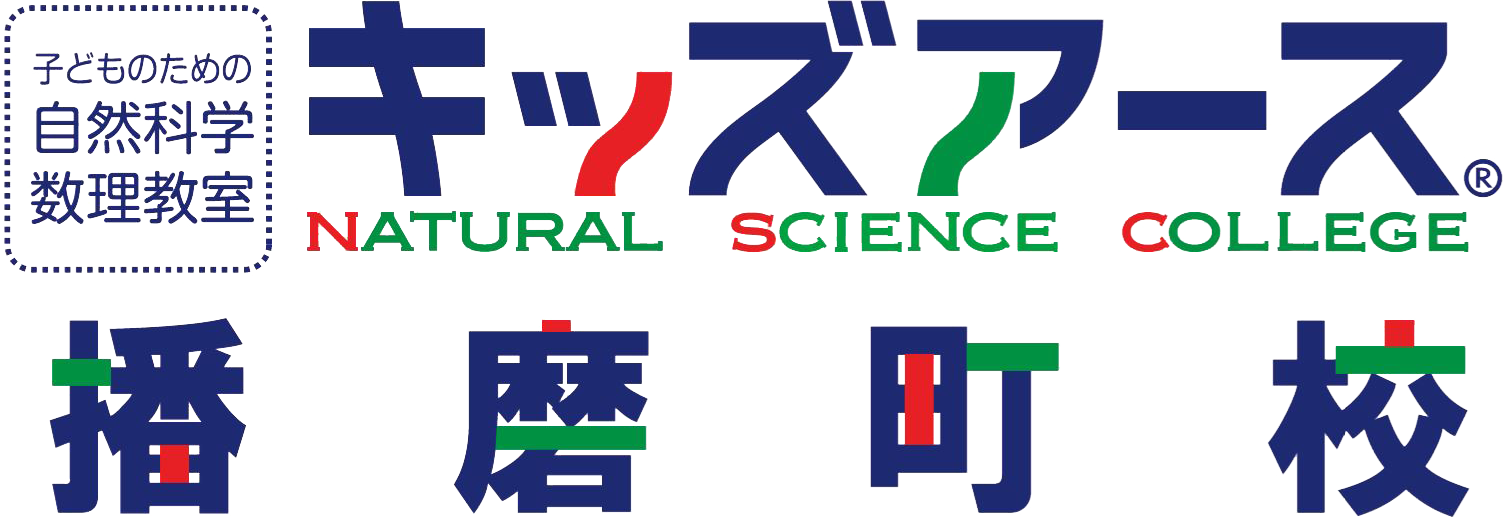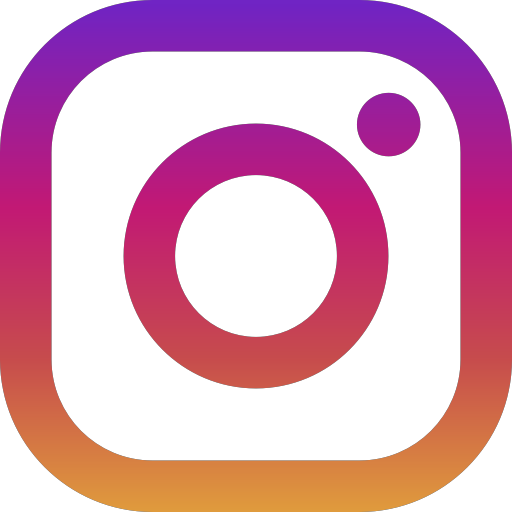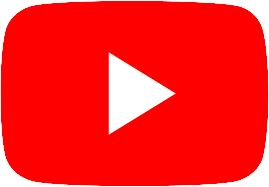ブログ・お知らせ
【夏休み企画】鍾乳洞を探検しよう!~「鍾乳洞」の秘密 編
- 04_イベント・講演会,05_見学・おでかけ,理科
SDGsアドバイザーが講師をつとめる、兵庫県の理科実験教室、キッズアース播磨町校です。


東大卒講師が勉強のノウハウを楽しく教える、播磨町の共明塾です。神戸、加古川、明石、高砂からも是非お越しください。
当サイトで常にアクセス数が多い「鍾乳石(しょうにゅうせき)実験」。
今年は、もう一度この実験を行うとともに、実際の「鍾乳洞(しょうにゅうどう)」にも行ってみることにしました。
事前に鍾乳洞(しょうにゅうどう)について調べてみましょう。
【鍾乳洞って何?】
「鍾乳洞(しょうにゅうどう)」は「洞窟(どうくつ)」の一種です。
自然にできた「洞窟(どうくつ)」は、どう出来たかで、いくつかに分類されます。
Wikipedia「洞窟」を参考にまとめると下記になります。
| 大分類 | 中分類 | でき方 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 火山洞窟 | リフト洞窟 | 溶岩が冷却・収縮する際に生じる割れ目や亀裂が 拡大してできる洞窟。 |
富岳風穴・鳴沢氷穴(山梨県) 万丈窟(済州島国家地質公園): 韓国観光公社 |
| ガス噴出孔洞窟 | 火山ガスの噴出によって周囲の岩石が 侵食・溶解されてできる洞窟。 |
||
| 溶岩洞窟 | 火山から流出した溶岩流の表面が固まり、 内部の溶岩が流れ去ることで形成される。 |
||
| 侵食洞窟 | 海食洞窟 | 波の浸食作用により、海岸の岩盤が削り取られてできる洞窟。 |
小樽 青の洞窟(北海道) 城ケ崎 伊豆半島ジオパーク (静岡県) |
| 湖食洞窟 | 湖の水位変動や波浪が湖岸の岩石を侵食してできる洞窟。 | ||
| 河食洞窟 | 河川の流水が河床や河岸の岩石を侵食・摩耗させてできる洞窟。 | ||
| 風食洞窟 | 風に含まれる砂粒などが岩石に衝突し、 摩耗させることでできる洞窟。 |
||
| 溶食洞窟 | 石灰岩洞窟 (鍾乳洞) |
石灰岩が二酸化炭素を含む地下水に溶かされてできる洞窟。 鍾乳石などが見られる。 |
秋吉台 (山口県) 岩泉町・龍泉洞(岩手県) 玉泉洞(沖縄県) Optimistic cave (ウクライナ) 氷の洞窟・アイスケーブ観光情報(アイスランド) |
| 石膏洞窟 | 石膏岩が水に溶かされてできる洞窟。 石灰岩洞窟に比べると規模が小さい場合が多い。 |
||
| 岩塩洞窟 | 岩塩が水に溶かされてできる洞窟。 乾燥地域や地層中に岩塩が存在する地域に見られる。 |
||
| 氷河洞窟 (氷洞) |
氷河の内部や底部が融解水によって溶かされてできる洞窟。 内部は氷で構成される。 |
||
| 構造洞窟 | 節理洞窟 | 岩盤の節理(規則的な割れ目)が、 風化や浸食により拡大してできる洞窟。 |
玄武洞(兵庫県) |
| 断層洞窟 | 地殻変動による断層のずれや、断層に沿って 岩石が破砕されることでできる洞窟。 |
||
| 地震洞窟 | 地震による地盤の変動や岩盤の崩落によって 一時的または恒久的に形成される洞窟。 |
もちろん、それぞれの作られ方が影響しあう(地震で出来た洞窟が、風によって削られるなど)こともありますから、必ずどれかに分類される、というわけではありませんが、様々な理由で洞窟が出来る、ということが分かります。
加えて、人間が掘った洞窟、資源を掘っていく中で作られた洞窟、自然に出来た洞窟に人間が手を加えたもの、など人工洞窟、あるいは手の加わった洞窟というのもあります。
さて、この中でも「鍾乳洞(しょうにゅうどう)」にだけ見られるものがあります。
それが「鍾乳石(しょうにゅうせき)」です。
「鍾乳石(しょうにゅうせき)」は、洞窟の中で見られる不思議な形の石です。


「鍾乳洞」は、雨水が地面にしみこみ、石灰岩という石を少しずつ溶かすことで、作られていきます。
この石灰岩を溶かしこんだ水が、洞窟の天井からポタポタと落ちるとき、水に溶けていた石の成分が固まって、氷のつららのように垂れ下がったものが「鍾乳石」です。
また、地面に落ちた水も、積み重なってタケノコのように伸びていきます。これは「石筍(せきじゅん)」と言います。
説明するのは簡単ですが、「鍾乳石」も「石筍」も、とても長い時間をかけて少しずつ大きくなっていくもので、簡単にできるものではありません。
【兵庫県に鍾乳洞はないの?】
兵庫県下には、淡路に「野島鍾乳洞」があるのですが、狭くて入れないとのこと。
野島鍾乳洞・兵庫県唯一の鍾乳洞/淡路島
この中で、日本で一番有名な鍾乳洞と言えば、山口県にある〈秋芳洞(あきよしどう)〉でしょう。





野島鍾乳洞・兵庫県唯一の鍾乳洞/淡路島
また、新温泉町には「鍾乳日本洞門」があります。
兵庫県に「洞窟」はいくつかありますが、「鍾乳洞」はあまり見当たりません。
兵庫県で一番有名な洞窟は、「玄武洞」でしょう。
これは、「構造洞窟」の一種です。
また、淡路島にも、神社として祀られている「洞窟」があります。
さらに、兵庫県では豊岡市、香美町、新温泉町にまたがる(京丹後市・鳥取市・岩美町も範囲)
には、数々の「洞門」があるそうです。
海辺の洞窟は「海食洞窟」「風食洞窟」に分類されることが多いですね。
【岡山の鍾乳洞へ行こう!】
兵庫県の隣、岡山県の高梁川周辺にはいくつかの鍾乳洞が点在します。
真庭市にある「備中鐘乳穴(びちゅうかなちあな)」
新見市にある「満奇洞(まきどう)」「井倉洞(いくらどう)」
鍾乳洞ではないですが「羅生門」「絹掛けの滝」も、この地形が生んだ景観です。
今回は行きませんでしたが、「備中鐘乳穴(びちゅうかなちあな)」は、
平安時代に著された「日本三大実録」にその名があり、
文献に残る日本最古の鍾乳洞なのだそうです。
今回は、「満奇洞(まきどう)」「井倉洞(いくらどう)」「羅生門」に足をのばしました。
【日本の有名な鍾乳洞】
日本三大鍾乳洞で調べると、龍河洞・龍泉洞・秋芳洞の三つが挙げられます。
この中で、日本で一番有名な鍾乳洞と言えば、山口県にある〈秋芳洞(あきよしどう)〉でしょう。
日本最大級の鍾乳洞で、国の特別天然記念物でもあります。
秋吉台のカルスト台地も見応えがあります。
公式サイト: 特別天然記念物 秋芳洞 | 秋吉台 公式ホームページ



(上記写真は フォトダウンロード|【公式】山口県観光/旅行サイト おいでませ山口へ より)
関西からだと、高知県にある〈龍河洞(りゅうがどう)〉も魅力的です。
見学コースとして、「観光コース」に加え、ヘルメット・ヘッドランプをつけ、ナビゲーターと共にまっくら闇を進む「冒険コース」、龍河洞を形成してきた上龍河からの地下水の流れを感じながら進む「西本洞コース/水の洞窟」もあるとのこと。
さらに、弥生時代の土器、石器も出土しており、「神の壺」と呼ばれる鍾乳石に包み込まれ一体化した土器を見ることも出来るそうで、考古学的な観点からも、とても面白い鍾乳洞です。
公式サイト: 国指定史蹟天然記念物 龍河洞
岩手県にあるのが〈龍泉洞(りゅうせんどう)〉。
ここも「岩泉湧窟及びコウモリ」として国の史跡名勝天然記念物に指定されています。
世界でも稀な透明度を誇る美しい地底湖が特徴で、8つの地底湖が確認されているそうです(公開されているのは3つ)。
龍泉新洞では、大昔の動物の骨や骨で作ったクシや縄文時代の土器や石器がたくさん見つかっているそうで、こちらも考古学的にも面白い鍾乳洞と言えますね。
公式サイト: 岩泉町・龍泉洞WEBサイト


(上記写真は 観光写真ダウンロード | いわての旅 より)
さて、では、百聞は一見に如かず。
岡山県新見市にある満奇洞に向かうことにしましょう!
オススメ記事
-
- お知らせ
-
- お知らせ
-
- お知らせ